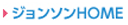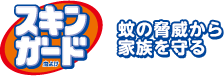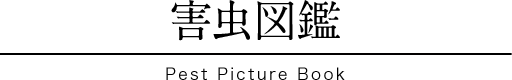アカイエカ

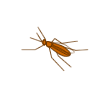
| 分類 | イエカ属 |
|---|---|
| 形態 | 成虫の体長は約5.5mmで、体色は淡赤褐色。 |
| 繁殖時期 | 早春〜晩秋 |
| 発生源 | 下水溝、どぶ、防火用水など |
| 生態・習性 | メスが産卵時に吸血する。吸血活動は10月頃まで続き、その後休眠状態に入り、メスの成虫は越冬する。日本で最も代表的な蚊で、主に夜間に活動し、夜、家の中に入ってきて刺したり、庭などで獲物を狙ったりする。活動範囲は数数百m〜数kmと広範囲。鳥類も好んで吸血することから、日本にウエストナイルウィルスが上陸した場合にウィルスを媒介する危険性が高いとされている。 |
ヒトスジシマカ

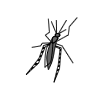
| 分類 | ヤブカ属 |
|---|---|
| 形態 | 成虫の体長は約4.5mm。黒色で、背中に一筋の白い線がある。 |
| 繁殖時期 | 夏期 |
| 発生源 | 空き缶、古タイヤ、植木鉢の皿、墓地の花立てなどにたまった水 |
| 生態・習性 | メスが、産卵時に吸血する。卵は乾燥に耐え、次に雨水がたまった時に孵化する。湿った落ち葉やコケなどにも産卵する。卵の状態で越冬する。庭ややぶにいて、昼間、人を刺す。吸血などの行動も素早く、敏捷でつかまえにくい。行動範囲は100〜150mと狭い。 デング熱を媒介する蚊として知られているが、ウエストナイルウィルスが日本に上陸した場合に主要な媒介蚊となると言われている。 |
チカイエカ

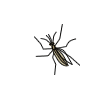
| 分類 | イエカ属 |
|---|---|
| 形態 | 成虫の体長は約5.5mm。アカイエカの亜種で非常によく似ている。 |
| 繁殖時期 | 通年 |
| 発生源 | 水洗トイレの浄化槽やビルの地下の溜まり水、地下鉄の側溝など |
| 生態・習性 | 吸血しなくても一回目の産卵をして繁殖できる。冬の蚊ともいわれるように、低温に強く、冬期も休眠しない。冬の吸血被害はこの蚊によるもの。都心のビル街でも問題になっているように、一年を通じて安定した環境を提供してもらえる都市化が進んだ地域ほど多く発生。住環境の変化に伴い、今後の増加が予想される。 ウエストナイルウィルスを媒介することができるといわれている。 |
ブユ(ブヨ)

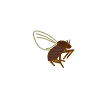
| 形態 | 成虫の体長は3〜5mm。ずんぐりとした小型のハエのような虫。吸血をするのは、アシマダラブユ、アオキツメトゲブユなどの数種類。 |
|---|---|
| 繁殖時期 | 主に5〜10月夏期 |
| 発生源 | 灌漑用水や川の岸辺や水中に垂れている植物の葉に産卵 |
| 生態・習性 | 幼虫、さなぎは水質のきれいな河川に生息するため、農村や、渓流、キャンプ場など山間部で多く発生。吸血するのは、蚊と同じでメスのみ。朝夕に活動し、集団で群れをなして襲うこともある。人の皮膚に傷をつけ、流れ出た血液をなめるように吸血する。蚊よりもかゆみがひどく、人によっては赤く腫れあがったり、水疱ができることも・・・。 |
ノミ

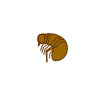
| 形態 | 翅(はね)が退化した昆虫の仲間。体は縦に扁平で、寄生する動物の毛や人間の皮膚の間を素早く動くのに適している。 |
|---|---|
| 寄生動物 | 人、犬、猫などの哺乳類。中世のヨーロッパを震撼させたペストは、ネズミに寄生するケオプスネズミノミが主な媒介者として知られている。 |
| 生態・習性 | 成虫の寿命は約1年。一生に200〜300個の卵を産む。幼虫は宿主の巣のゴミに含まれる有機物や自分の親のフンなどを食べて成長。成虫になると宿主に寄生し、オスもメスも吸血する。長い後ろ脚で体長の約200倍も跳躍する。 |
イエダニ

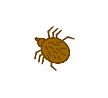
| 形態 | 成虫の体長は0.5〜1mm。汚白色をしているが、吸血すると赤黒くなる。 |
|---|---|
| 寄生動物 | ネズミ |
| 繁殖時期 | 春秋がピークだが、年間を通じて繁殖 |
| 生態・習性 | 雌は生涯で約100個の卵を産む。卵は、約2週間で成虫に成長する。成虫は主にネズミに寄生し、ネズミの血を吸って生活している。ネズミが死んだり、ネズミの体から落下するなどして宿主から離れると、人やペットなどを吸血する。 |